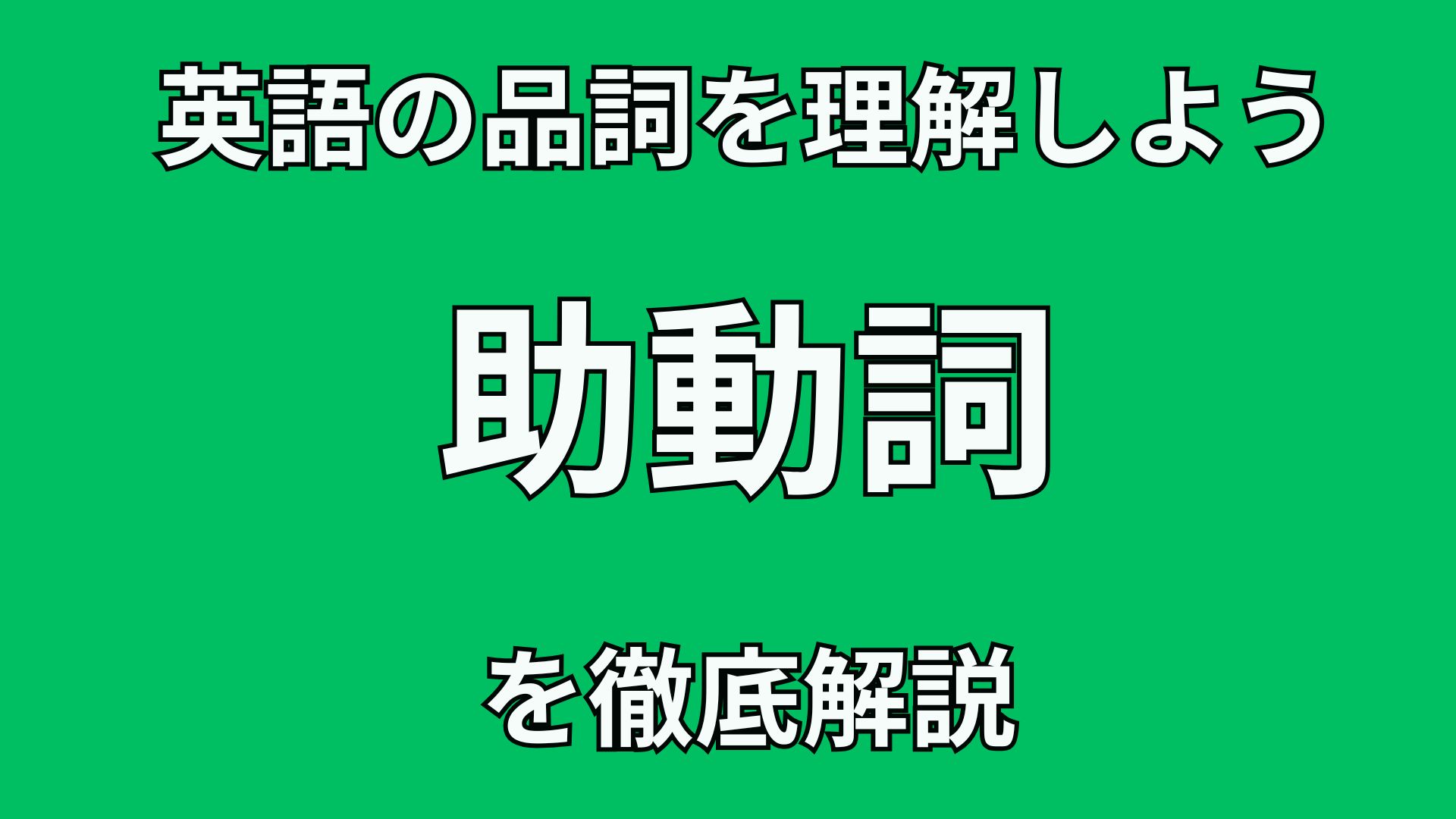
英語の助動詞とは?

英語の助動詞(Auxiliary Verbs / Modal Verbs)を一言でまとめると以下のとおりです。
助動詞は
本動詞の前に置かれて、動詞に特別な意味(可能・推量・義務・許可など)を加える品詞
です。
分かりやすくいえば
”話し手の情報を動詞に補足する役割”
ということですね。
例えば
”行く(go)”という動詞だけだと、ただの”行く”という意味になりますね。
これに助動詞をつけることで以下のような表現をすることが可能となります。
can go → 「行ける」(能力や可能性)
will go → 「行くつもり」(未来の意志)
should go → 「行くべき」(助言)
must go → 「行かないとダメ」(義務)
このように、動詞に
「どういう気持ちでその動作をするのか」
を伝えるのが助動詞の役割です。
つまり
”動詞を補助する動詞”
助動詞になります。
英語の助動詞の文法的役割とは?

英語の助動詞は文の中で以下のような文法的役割を持ちます。
動詞の前に置かれて、「可能性」「義務」「許可」「意志」などを表す
助動詞の文法的役割はこれだけです。
覚えかたのイメージとしては
”助動詞は動詞に「どういう気持ちでその動作をするのか」を伝えるもの”
という認識でOKです。
英語の助動詞と動詞の違いとは?

助動詞と動詞って何が違うの?
なおう人も多いのではないでしょうか?
どちらも同じ”動詞”だから使い分けがよく分からない人もいるかもしれませんね。
ここで英語初心者がつまずきやすい助動詞と動詞の明確な違いについて少し解説しておきましょう。
英語の助動詞と動詞はその役割と意味の性質が違います。
これを分かりやすく表にまとめるとこんな感じとなります。
| 助動詞 | 動詞 | |
| 文法的役割 | 動詞を補助する(助ける) | 文の中心的な意味を表す(行動や状態) |
| 意味の性質 | 単独では意味があいまい | 単独で意味が成り立つ |
| 例 | can, will, must, should など | run, eat, know, go, sleep など |
例文でみてみましょう。
I can swim.(私は泳ぐことができる)
この文は”can”が助動詞で、”swim(泳ぐ)”という動作に”可能”を加えています。
I can.(私はできる)
”can”単体だけで使用しても”できる”という意味をぼんやり表すだけで、何ができるのか分からないですよね。
だからその直後の”swim”という動詞を補う必要があるということです。
よく分からなければ
”役割は動詞のサポートで単独では意味があいまいになるものが助動詞 中心的存在となり単独でも意味が通じるものが動詞”
という認識でOKかと思います。
英語の助動詞の種類

英語の助動詞には主なものとして以下のようなものがあります。
・can/could
・will/would
・shall/should
・may/might
・must
とりあえずこの9個を理解しておけば基本的な英会話で困ることはないでしょう。
それぞれ詳しく解説していきますね。
可能・能力を表す can/could
can/couldは
”(~できる)(できたかもしれない)といった可能・能力”
を表します。
couldはcanの過去形でcouldを使うとより丁寧な表現が可能となります。
使い方の違いは以下のようになります。
| can | could | |
| 時制 | 現在形 | 過去形 |
| 意味 | ~できる | ~できた・~できたかもしれない・~できるかもしれない |
| 使い方 | 可能・能力・許可 | 過去の能力・丁寧な依頼・仮定 |
それぞれ例文をみていきましょう。
まずはcanから。
① can 可能(~できる)
I can swim.
(私は泳げます)
② can 能力(能力がある)
She can speak French.
(彼女はフランス語を話せます)
③ can 許可(~してもよい)
You can go now.
(もう行っていいですよ)
④ can 否定(~できない)(can't / cannot)
I can't drive.
(私は運転できません)
つづいてcouldですがcouldにはcanの過去形で(~できた)という”過去の能力”の意味だけではなく「丁寧・仮定・可能性」などといった意味もあります。
① could 過去の能力(~できた)
I could swim when I was a child.
(子供のころは泳げました)
② could 丁寧な依頼・提案(主に疑問文で使用)
Could you help me?
(手伝っていただけますか?)
→ 「can you」より丁寧な表現
③ could 仮定法(~できるだろうに)
If I had time, I could help you.
(時間があれば手伝えるのに
④ could 可能性(~かもしれない)
It could rain later.
(後で雨が降るかもしれない)
意思を表す will/would
will/wouldは
”(~するつもり)(~するつもりだった)といった未来の意思や予測、過去の仮定”
を表します。
wouldはwillの過去形でwouldを使うとより丁寧な表現が可能となります。
使い方の違いは以下のようになります。
| will | would | |
| 時制 | 現在形・未来形 | 過去形 |
| 意味 | ~するつもり | ~するつもりだった、~だろうに(仮定)、丁寧な依頼など |
| 使い方 | 未来の予測・意思・約束 | 仮定法、丁寧表現、過去の習慣、控えめな表現など |
それぞれ例文をみていきましょう。
まずはwillから。
① will 未来の予測(~するだろう)
It will rain tomorrow.
(明日は雨が降るでしょう)
② will 意志・意欲(~するつもり)
I will help you.
(手伝いますよ)
③ will 約束・決意
I will never lie to you.
(絶対にあなたに嘘はつきません)
④ will 命令・要求(強めの口調)
You will do it now!
(今すぐそれをやりなさい!)
wouldはwillの過去形のように見えますが、”仮定”や”丁寧表現”として使う場面が多いです。
「If ~」のような仮定の文でwouldを使うのが典型的です。
① would 仮定法(もし~なら、~するだろう)
If I were you, I would study more.
(私があなただったら、もっと勉強するのに)
② would 丁寧な依頼(控えめ)
Would you open the window?
(窓を開けていただけますか?)
③ would 過去の意志(~するつもりだった)
He said he would call me.
(彼は電話するつもりだと言っていた)
④ would 過去の習慣(~したものだ)
When I was a child, I would play outside every day.
(子供の頃、毎日外で遊んでいたものだ)
⑤ would 控えめな表現・遠回しな言い方
That would be nice.
(それはいいですね)⇒will beより柔らかい言い方
wouldとcouldの使い方の違いとは?
ここまで見てきて、

wouldとcouldって似たような使い方だけどどうやって使い分けているの?
と思った人は鋭いです!!
wouldとcouldはどちらも丁寧な表現や仮定の文でよく使われる助動詞ですが、
「実際の会話のときにどちらを使えばいいの?」
と悩むかもしれませんね。
実はこの2つは意味や使い方に明確な違いがあります。
イメージはこんな感じですね。
・would・・意思
・could・・可能性
| would | could | |
| 元の形 | will(意思・未来) | can(能力・可能性) |
| 意味 | 意思・仮定・丁寧な依頼 | 能力・可能性・丁寧な依頼 |
| 仮定文の意味 | ~するだろうに | ~できるだろうに |
| 丁寧な依頼の意味 | ~してくれませんか?(意思を問う) | ~して頂けませんか?(可能性を問う) |
特に仮定文と丁寧な依頼での使い分けは迷うところだと思うので例文で解説していきます。
① wouldとcouldの”仮定文”での違い
If I were rich, I would buy a big house.
(お金持ちなら、大きな家を買うのに)
wouldは
”買う意思や行動がある”
というニュアンスになります。

私がお金持ちだったら大きな家を買っていたのに・・・
つまり”買う”という意思にフォーカスが当たっていますね。
それに対してcouldは・・
If I were rich, I could buy a big house.
(お金持ちなら、大きな家が買えるのに)
couldは
”買う能力や可能性がある”
というニュアンスになります。

私がお金持ちだったら大きな家が買えたのに・・
こちらは”買うことができた”という可能性にフォーカスが当たっているのが分かりますね。
ちょっとややこしいかもしれませんがイメージをとらえることができればすんなりと頭に入ってくると思います。
仮定法はちょっとややこしいですのでこちらの記事でも詳しく解説しています。
※関連記事
仮定法について詳しく解説
② wouldとcouldの”丁寧な依頼”での違い
この2つは日本語訳にすると意味はほとんど変わりません。
どちらを使っても間違いではないんですが
”couldを使った方が遠回しでより丁寧”
とされています。
Would you open the window?
(窓を開けてくれますか?)
wouldは
”「開けるつもりはありますか?」という意志を問う”
というニュアンスになります。

窓開けてもらっていいですか?(あなたに窓を開ける意思はありますか?)
つまり”窓を開けてもらえますか”という相手の意思にフォーカスが当たっていますね。
Could you open the window?
(窓を開けていただけますか?)
couldは
”「開けることができますか?」という可能性や能力を問う”
というニュアンスになります。

窓開けていただけますか?(あなたに窓を開けることはできますか?)
つまり”窓を開けることができるか?”という相手の可能性にフォーカスが当たっていますね。
今までの説明で・・
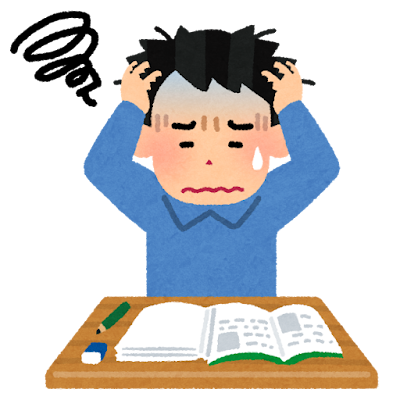
ほとんど同じニュアンスに聞こえるしよく分からん・・・
という人は
”couldの方がより丁寧で初対面の人に尋ねるときはwouldよりもcouldを使う”
という認識でいいかと思います。
ただこういった理屈を理解しておくことは重要です。
提案・助言・義務・推量を表す shall/should
shall/shouldは
”(~すべき)(~した方がいい)(~しましょうか?)(~のはず)といった提案・助言・義務・推量”
を表します。
shouldはshallの過去形になります。
ちなみにshallは(提案・申し出)といった疑問文以外ではあまり使用されずやや古風な言い回しとなるようです。(主にイギリス英語で使われる)
使い方の違いは以下のようになります。
| shall | should | |
| 時制 | 現在形 | 過去形 |
| 意味 |
~しましょうか? |
~すべき・~するのが当然・~のはず |
| 使い方 | 提案・申し出 | 仮定法、丁寧表現、過去の習慣、控えめな表現など |
それぞれ例文をみていきましょう。
まずはshallから。
提案・申し出(Shall I / Shall we ~?)
Shall we dance?
(踊りましょうか?)
Shall I open the window?
(窓を開けましょうか?)
Shall I help you?
(お手伝いしましょうか?)
Shall we meet at 3?
(3時に会いましょうか?)
shallでもっとも頻出パターンは
”何かを提案したり、自分の行動について相手にたずねる表現”
です。
shallは(私が~しましょうか?)といった丁寧な言い回しになるのですが似たような丁寧な表現でwouldやcouldもありましたよね。
ちょっと頭がこんがらがりそうですがこの3つの明確な使い分けもここで覚えておきましょう。
| shall I~? | would you~? | could you~? |
|
(私が)~しましょうか? |
(あなたに)~していただけますか? | (あなたに)~していただけますか? |
| 自分がすることを申し出る | 相手にお願いする | 相手にお願いする |
| 自分から提案 | 丁寧 | より丁寧 |
shallは
”自分から相手に提案”
なので主語は自分(I)となります。
これに対してwouldとcouldは
”相手に丁寧に依頼”
するので主語はあなた(you)になります。
それぞれを例文で違いをみていきましょう。
Shall I open the window?
(窓を開けましょうか?)⇒「自分から窓を開けましょうか?」という提案
Would you open the window?
(窓を開けてくれますか?)⇒「相手に窓を開ける意思があるか?」という意思の確認(丁寧)
Could you open the window?
(窓を開けていただけますか?)⇒「相手に窓を開ける可能性があるか?」という可能性の確認(より丁寧)
shallを使用する場合はあくまで主語は自分なので、
”shall you~”という表現はないんですね。
続いてshould。
① should 助言・忠告(~すべき)
You should eat more vegetables.
(もっと野菜を食べるべきです)→「~した方がいいよ」というアドバイス
② should 義務・当然(~するのが当然)
Students should be on time.
(生徒は時間を守るべきだ)
③ should 推量(~のはず)
She should be home by now.
(もう家に着いているはずです)→「可能性が高い」ときにも使用可(90%くらいの確信)
④ should 仮定法(if ~ の中や、仮定の文)
If you should need help, let me know.
(もし万が一助けが必要なら教えて)
許可・可能性・推量を表す may/might
may/mightは
”(~してもいい)(~かもしれない)といった許可・可能性・推量”
を表します。
mightはmayの過去形になりますが過去という意味で使用されることは少ないです。
使い方の違いは以下のようになります。
| may | might | |
| 時制 | 現在形 | 過去形 |
| 意味 |
~かもしれない(50%) ~してもよい |
~かもしれない(30%) |
| 使い方 | 推量・許可 | 推量・仮定 |
それぞれ例文をみていきましょう。
まずはmayから。
① may 推量「~かもしれない」50%くらいの可能性
It may rain tomorrow.
(明日雨が降るかもしれません)
② may 許可「~してもよい」
May I go to the bathroom?
(トイレに行ってもいいですか?)
この表現はややフォーマルな言いまわしになります。カジュアルに言いたいときは
”Can I~”
を使うのが一般的ですね。
続いてmight。
① might 推量「~かもしれない」30%くらいの可能性
It might rain tomorrow.
(明日雨が降るかもしれません)⇒mayより可能性が低く控えめに表現
② might 仮定・控えめな表現
I might be wrong, but I think she’s from Canada.
(間違ってるかもしれませんが、彼女はカナダ出身だと思います)⇒自信がないとき、やんわり言いたいときに使用
May I~?とShall I~?の違い
ここまで読んできてこの疑問点に気づいた人は多いのではないでしょか?
どちらも主語が自分(I)で言い回しが似ていますが実は意味合いが全く違うので注意が必要です。
この2つの言い回しの違いは以下のとおりです。
| May I~? | Shall I~? |
| ~してもいいですか? | ~しましょうか? |
| イメージ | |
| 相手の許可を求める | 自分から提案するだけ |
これも理屈で覚えると頭がこんがらがるので会話のイメージで理解しましょう。
会話のイメージはこんな感じです。

May I come in?(入っていい?)
⇒相手に入っていいかどうか許可を求めている

Yes, of course.(もちろんいいですよ)

Shall I call a taxi for you?(タクシー呼びましょうか?)
⇒相手のためにタクシーを呼ぶという提案の申し出

Oh, thank you!(えーありがとう!)
上記の会話を見てもらえればお分かりだと思うのですが
”May I~”の場合は相手に(~してもいいかどうか?)という許可を求めているのに対して、
”Shall I~”は(~しましょうか?)自分から提案しているだけで特に相手の許可は求めていませんね。
このように相手の許可のニュアンスがあるかどうかが”May I~”と”Shall~”の使い分けのポイントとなります。
義務・禁止・強い推量を表す must
mustは
”(~しなければならない)(~に違いない)(~してはいけない)といった義務・強い推量・禁止”
を表します。
mustは過去形がないため、過去の義務を表すときは”had to”を使います。
日本語で言う
”絶対に〜しなさい”
に近いイメージですね。
例文をみてみましょう。
① must 義務・必要(〜しなければならない)
You must wear a seatbelt.
(シートベルトをしなければなりません。)
Students must do their homework.
(生徒は宿題をやらなければなりません。)
ちなみにmustと似たような表現で、
”have to"
というものがありますがmustの方が話し手の意向が強いイメージです。
② must 強い推量(〜に違いない)
「きっと〜だ」
「〜に違いない」
と、話し手が確信している時に使います。
He must be tired after such a long trip.
(あんなに長い旅行のあとだから、彼はきっと疲れているに違いない。)
This must be the right place.
(ここがきっと正しい場所に違いない。)
③ must not 禁止(〜してはいけない)
”must not~”で
「〜してはいけない」
と強い禁止を表します。
You must not smoke here.
(ここでタバコを吸ってはいけません。)
Students must not cheat on exams.
(生徒は試験でカンニングしてはいけません。)
英語の助動詞の使い方のルール

英語の助動詞は以下のような文法的ルールがあります。
文法ルールといっても絶対に覚えるべきルールはこの3つだけですのでおさえておきましょう。
・必ず”主語 + 助動詞 + 動詞の原形”
・否定文の場合は助動詞のあとに ”not”をつける
・疑問文の場合は助動詞を文頭にする
ではそれぞれ説明していきますね。
必ず”主語+助動詞+動詞の原形”
”主語+助動詞+動詞の原形”
これは英語で助動詞を使うときの鉄則ルールです。
助動詞のすぐ後ろには、動詞の原形を置きます。
でも英語初心者の中にはもしかすると・・・

”動詞の原形”って何?何が原形なの?
という人がいるかもしれませんね(笑)
そもそも
”動詞の原形というものが何か分からない”
という人もいるでしょう。
”動詞の原形”は英文法を学ぶ上で非常に重要なものですのでここで軽く解説しておきます。
動詞の原形とは?
動詞の原形とはシンプルにいえば
”何も変化していない動詞そのままの形”
のことをいいます。
例えば・・
go(行く)
eat(食べる)
study(勉強する)
これらは全て動詞の原形となります。
ここまではいいのですが
”英語の動詞というのは使い方によって様々な形に変化する”
という面倒くさいルールがあるんですね。
英語の動詞の変化のパターンはこの5種類になります。
① 原形
② 三人称単数現在(三単現)
③ 過去形
④ ing形
⑤ 過去分詞
原形というのは動詞の基本パターンです。
つまり英語の動詞は使い方によって原形からこの5パターンに変化するんですね。
さきほどの「go 」「eat 」「study」をこの5パターンに変化させるとこのようになります。
| 原形 | 三単現 | 過去形 | ing系 | 過去分詞 |
| go | goes | went | going | gone |
| eat | eats | ate | eating | eaten |
| study | studies | studied | studying | studied |
動詞の原形は語尾が変わっていないのが分かりますよね。
つまり
”英語の辞書に掲載されている動詞そのままの形(基本形)”
これが英語の動詞の原形となります。
これを理解した上で本題に入ります。
”主語+助動詞+動詞の原形”の例文
”主語+助動詞+動詞の原形”について例文をみていきましょう。
I can go.
(私は行けます。)
You should come.
(あなたは来るべきです。)
He can swim.
(彼は泳げる。)
We will go.
(私たちは行くつもりです。)
すべての文で助動詞のあとは動詞の原形となっていますね。
助動詞を使う場合は助動詞の後は動詞の原形以外のものは置いてはいけないルールとなっています。
だからこのように助動詞の後に動詞の原形以外のものがつく文は文法上全て間違いなんですね。
(誤)I can to go.
⇒(正)I can go.
(誤)She will goes.
⇒(正)She will go.
(誤)You must studies.
⇒(正)You must study.
これは英語初心者の人がよく犯しがちなミスなのでまずこの基本形をしっかりおさえておきましょう。
否定文の場合は助動詞のあとに”not"をつける
英語で助動詞を使った否定文を作りたいときは、
”助動詞のすぐあとに not をつける”
というルールがあります。
これは、
”助動詞そのものが否定文や疑問文を作る力を持っている”
からなんですね。
英語の否定文を作るときは動詞の前に、
「do not / does not / did not」
をつける必要があります。
She sings.(彼女は歌います。)
⇒She does not sing.
(彼女は歌いません。)
否定文の作り方の基本について詳しくは関連記事をご覧ください。
※関連記事
英語の否定文の作り方を解説
しかしこの文に助動詞が使われるとこのようになります。
She can sing.(彼女は歌えます)
⇒ She cannot sing.(彼女は歌えません)
助動詞canそのものがdo/does/didの働きをしているのであえてdo/does/didをつける必要がありません。
だから、
”She does not can sing.”
というのは文法上間違いですので注意しましょう。
よく使う助動詞の否定形のパターンをあげておきます。
| 助動詞 | 否定形(短縮形) | 意味 |
| can | cannot(can't) | 〜できない |
| will | will not(won’t) | 〜しないつもりだ |
| must | must not(mustn’t) | 〜してはいけない(禁止) |
| may | may not | 〜でないかもしれない |
| should | should not(shouldn’t) | 〜すべきではない |
なお実際の英会話では(can't)などの短縮形の方がよく使われますのでしっかり覚えておきましょう。
助動詞を使った否定文の基本構造は
”主語 + 助動詞 + not + 動詞の原形”
が基本となります。
I will not go to the party.
(私はそのパーティーに行きません)
You should not eat too much.
(食べ過ぎるべきではありません)
They may not come today.
(彼らは今日来ないかもしれません)
とにかく助動詞を使った否定文は
”「do not / does not / did not」は使わず助動詞の後にnotをつける”
という認識でOKです。
疑問文の場合は助動詞を文頭にする
英語で助動詞を使った疑問文を作りたいときは、
”助動詞を主語の前に置く”
というルールがあります。
これは「Yes / No で答えられる質問」を作る基本の形です
助動詞を使った疑問文の基本文型は、
"助動詞 + 主語 + 動詞の原形 + 〜?"
となります。
いずれも”主語が(~ですか?)”の意味になります。
それぞれ例文でみてきましょう。
Can+主語(〜できますか?)
Can you swim?
(あなたは泳げますか?)
Can she speak English?
(彼女は英語を話せますか?)
Will+主語(〜するつもりですか?)
Will you come to the party?
(あなたはパーティーに来ますか?)
Will it rain tomorrow?
(明日雨が降るでしょうか?)⇒天候を表す場合は主語がitとなる
Must+主語(〜しなければなりませんか?)
Must I finish this today?
(私は今日これを終えなければなりませんか?)
Must we wear a uniform?
(私たちは制服を着なければなりませんか?)
Should+主語(〜すべきですか?)
Should I call her now?
(私は今彼女に電話すべきですか?)
Should we take an umbrella?
(私たちは傘を持って行くべきですか?)
May+主語(〜してもよいですか?)※丁寧な許可を求める
May I use your pen?
(私はあなたのペンを使ってもいいですか?)May we ask a question?
(私たちは質問してもいいですか?)
ここで重要なポイントがあります。
冒頭にも述べましたが
”助動詞のあとは常に動詞の原形がくる”
というルールでしたよね。
文が疑問文になっても同じで
”助動詞を使った疑問文の場合の動詞は必ず原形”
というルールがあります。
これも間違いやすいポイントなのでしっかりおさえておきましょう。
(誤)Can she drives?
→ drives は三単現なのでNG)
(正)Can she drive?
またここでこのような疑問点があるかもしれませんね。

”Can she drive?”は”Does can she drive?”ではダメ?一般動詞で疑問文を作るときは文頭がDoとかDoesじゃないの?
結論から申し上げますとこれは文法上間違いです。
確かに英語の疑問文を作るときで動詞が一般動詞の場合は、文頭に
「Do / Does / Did」
をつける必要があります。
She drives.
(彼女は運転します)
⇒Does she drive?
(彼女は運転しますか?)
疑問文の作り方の基本について詳しくは関連記事をご覧ください。
※関連記事
英語の疑問文の作り方を解説
しかしこの文に助動詞が使われるとこのようになります。
She can drive.
(彼女は運転できます。)
⇒Can she drive?
(彼女は運転できますか?)
これも助動詞を使った否定文と同じ理屈で、
助動詞canそのものがdo/does/didの働きをしているのであえてdo/does/didをつける必要がありません。
だから、
”Does can she drive?”
というのは文法上間違いとなります。
助動詞の疑問文に対する答え方
助動詞の疑問文に対する答え方は、
”助動詞をそのまま使って答える”
というルールがあります。
答え方のパターンは、
Yes, 主語 + 助動詞.
No, 主語 + 助動詞 + not.
となります。
例文でみてみましょう。
Can she swim?
(彼女は泳げますか?)
→ Yes, she can. / No, she can't.
Will you come tomorrow?
(明日来ますか?)
→ Yes, I will. / No, I won't.
Should we leave now?
(もう出発すべきですか?)
→ Yes, we should. / No, we shouldn't.
ポイントは、
”Yes / No のあとは、必ず助動詞を入れる”
”短く答えるときも、主語と助動詞は省略しない”
”否定形では、助動詞+not を正しく使う(短縮形もOK)”
ということです。












