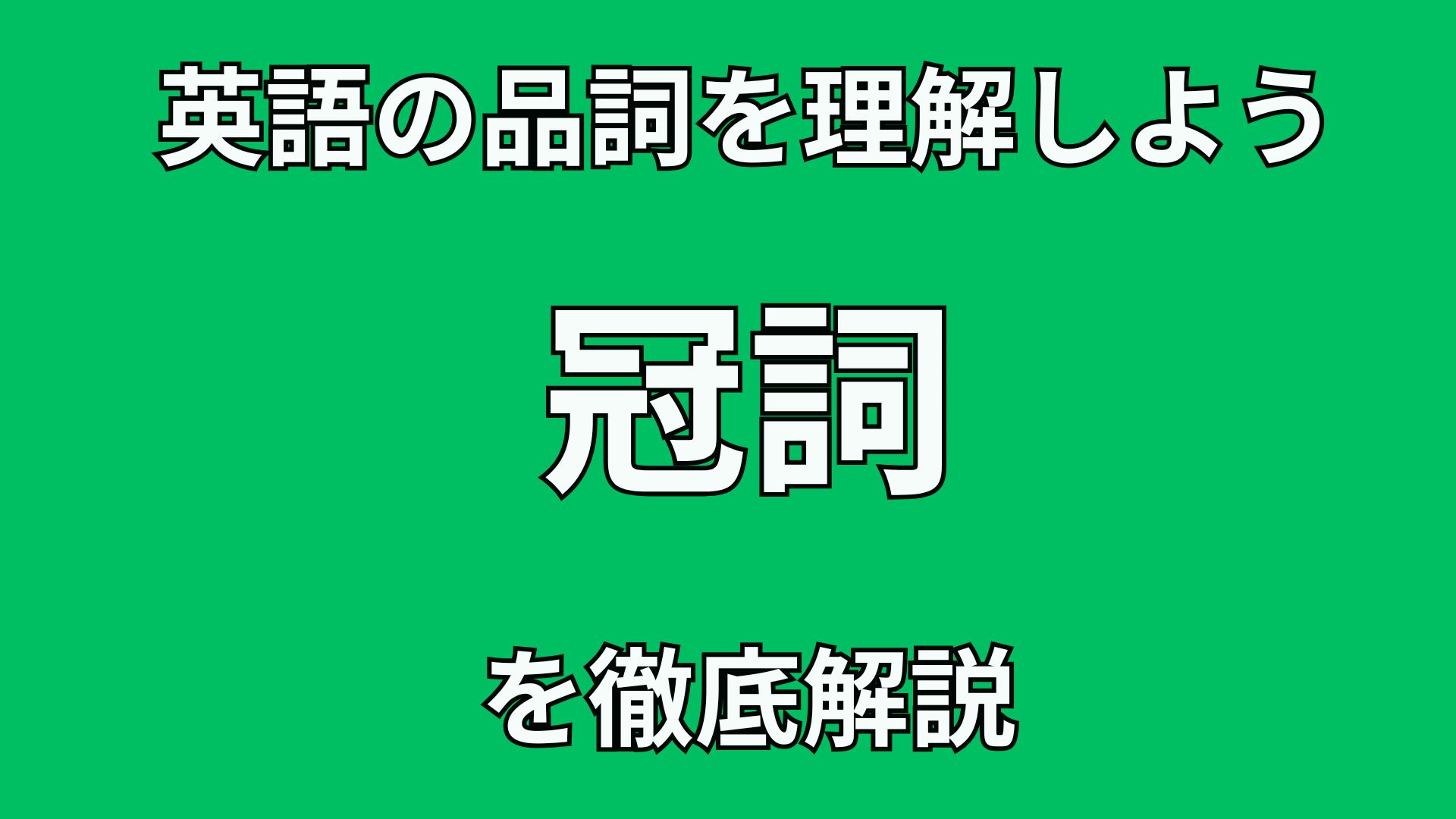
英語の冠詞とは?

英語の冠詞(articles)を一言でまとめると以下のとおりです。
冠詞は
名詞の前のおかれてその名詞が”特定か?単数か?”を示す
いわば文法上の目印です。
冠詞そのものには大きな意味は持たず
”名詞が単数であったり、特定のものである場合は文法上必要なもの”
ということですね。
英語の冠詞の文法的役割とは?

英語の冠詞は文の中で以下のような文法的役割を持ちます。
名詞の前に置いて、その名詞が「特定のもの」か「不特定のもの」かを示す
冠詞の文法的役割はこれだけです。
覚えかたのイメージとしては
”冠詞は「その名詞が話し手・聞き手にとってわかっているものか?そうでないか?」を区別するもの”
という認識でOKです。
冠詞というのは日本語にはない概念ですのでちょっとややこしいですが覚えてしまえば何てことないですのでサクッと理解してしまいましょう。
英語の冠詞の種類

英語の冠詞の種類はこの3つのみとなります。
・a/an (不定冠詞)
・the (定冠詞)
また名詞には、
”冠詞がつかないパターン”
もあります。
また
”a / an”を使用するときは名詞は必ず単数形
”the"を使用するときは名詞は単数でも複数でもOK
というルールがあります。
それぞれどんな違いがあるのでしょうか?
不定冠詞(a / an) 特定されていない単数の名詞につける
”a / an”は
「1つの〜」「ある〜」という意味で、
特定されていない単数の可算名詞の前
につけます。
特定されていない名詞につけるから
”不定冠詞”
といいます。
でもここで、

”特定されていない単数の可算名詞”ってどういうこと?
と思っている人が多いと思うので
”特定されていない名詞”
について少し解説しますね。
可算名詞については関連記事で詳しく解説していますのでご覧ください。
”特定されていない名詞”とは?
特定されていない名詞とは
”話し手も聞き手も、まだどれのことかはっきりわかっていない名詞”
のことをいいます。
たとえば会話の中で、
”はじめて出てくるものや人”
は相手はそれがどれのことか分からないですよね。
分かりやすく日本語でみてみましょう。

ねぇねぇ 公園で1匹の犬を見たよ。(どの犬とは言わずただ犬が一匹いたというだけ)

そうなんだ(どの犬なんだろう・・)
この場合の話し手の心理は
「どの犬か分からないけど犬という生き物を公園で見た」
というニュアンスです。
つまり会話のやりとりの中では”犬”という名詞が初登場で知られていない情報なんです。
この時点では”犬”は特定されていない名詞になります。
特定されていない名詞でなのでこの場合はdog(犬)の前に不定冠詞のaをつける必要があるんですね。

Hey, I saw a dog in the park.
分かりやすくいえば、
”会話の中でまだお互いの共通認識のないはじめて出てくる名詞”
というものが
”特定されていない名詞”
という認識でいいかと思います。
これを理解した上で不定冠詞a/anの詳しい使い方をみていきましょう。
不定冠詞(a / an)が使われるパターン
不定冠詞(a/an)が使われるパターンは基本この4つとなります。
① はじめて出てくる
② 一般的な例
③ 職業や役割
④ 単数で可算名詞
表にまとめるとこんな感じです。
| 状況 | 例文 | イメージ |
| はじめて出てくる | I saw a bird. | 聞き手はどの鳥かまだ知らない |
| 一般的な例 | I want a car. | どの車でもいいから1台欲しい |
| 職業や役割 | She is a doctor. | ある医師ということで不特定 |
| 単数で可算名詞 | He bought an apple. | リンゴ1個 |
a/anは複数系や特定されている場合には使いません。
(誤)I saw a dogs.(×)
⇒(正)I saw dogs.
dogsは複数なので冠詞は不要。または「some dogs」などを使う。
また人の名前などといった固有名詞には冠詞自体がつきませんのでご注意ください。
(誤) I met a John yesterday.
⇒(正) I met John yesterday.
aとanの使い分け
aとanの使い分けについては、
”直後の名詞の最初が母音か子音か”
で使い分けます。
英語の母音とはアルファベット26文字で
”a, i, u, e, o”
のことをいいます。
母音の発音は、
”口を開けて「あー」「いー」「うー」と発音するような音”
ですね。
日本語でいえば
”あ・い・う・え・お”に当たる音
になります。
an apple → 名詞が「ア」で始まる=母音の音
an egg → 名詞「エ」で始まる=母音の音
a cat → 名詞が「カ」で始まる=子音の音
母音ではじまる単語をいくつかあげてみました。
| 母音 | 主な単語 | 音 |
| a | apple, ant | ア |
| i | igloo, insect | イ |
| u | umbrella, uncle | ア/ウ(語による) |
| e | elephant, egg | エ |
| o | orange, ostrich | オ |
これ以外の音は全て子音になります。
つまりaとanの判断基準は
”母音ではじまる名詞がくるときはanを使用”
”それ以外はaを使用する”
という認識で基本OKなんですが、
勘違いしてもらいたくないのは
”判断基準は音であってスペルではない”
ということ。
これ結構勘違いして覚えてる人が多いようです(僕もそうでした)
というのも英語では
”単語の最初のスペルが母音(a, i, u, e, o)でも発音が子音で始まる単語”
というものがあります。
特にスペルがuとeuではじまる単語には要注意です。
| 単語 | 発音 | 正しい冠詞 |
| university | 最初が「ユ」子音ではじまる | a university |
| unicorn | 最初が「ユ」子音ではじまる | a unicorn |
| European | 最初が「ユ」子音ではじまる | a European |
| unit | 最初が「ユ」子音ではじまる | a unit |
| use(名詞) | 最初が「ユ」子音ではじまる | a use |
基本的には
最初のスペルが母音(a, i, u, e, o)の場合は音も母音の場合が多いのでスペルで判断するのもOKなんですがuとeuではじまる単語が出てきたら
「もしかすると発音が違うかも・・」
くらいの意識を持つといいでしょう。
定冠詞(the) 特定されている名詞につける
”the”は
「その〜」という意味で、
特定されている可算名詞や不可算名詞の前
につけます。
特定されている名詞につけるから
”定冠詞”
といいます。
ポイントは
”a/anは可算名詞のみ使用できたのに対しtheは可算名詞でも不可算名詞でも使用できる”
ということ。
特定されている名詞とは
“あれ”とか“その◯◯”みたいに、相手と共有してる話題やモノ”
のことを表す名詞のことですね。
分かりやすく先ほどの会話でみてみましょう。
Hey, I saw a dog in the park.

ねぇねぇ 公園で1匹の犬を見たよ。(どの犬とは言わずただ犬が一匹いたというだけ)

そうなんだ(どの犬なんだろう・・)
この時点では
「どの犬か分からないけど犬という生き物を公園で見た」
というニュアンスでしたよね。
その後の会話で話し手からこのように会話を続けました。

その犬はとても可愛かったよ。(公園にいたその犬が可愛かった)
この文では
「公園にいたその犬が可愛かった」
ということでどの犬かというのが特定されていますよね。
”公園にいた犬”
というのは最初のお互いの会話で既に共有しています。
だからこの場合は
"the dog"
となります。

The dog was so cute.
定冠詞(the)が使われるパターン
定冠詞”the”が使われるパターンですが主にこの6パターンとなります。
① すでに出た名詞
② どれか分かるもの
③ 世界に1つだけのもの
④ 固有の地名や機関名
⑤ 形容詞+the(集団を表す)
⑥ 楽器や発明品を語るとき
表にまとめるとこんな感じです。
| パターン | 例文 | イメージ |
| すでに出た名詞 |
I saw a cat. The cat was cute. |
前に出てきたものを再び言う |
| どれか分かるもの | Please open the window. | 文脈や状況で相手に(その~)と伝える |
| 世界に1つだけのもの | The sun is bright. | 唯一の存在だから特定されてる |
| 固有の地名や機関名 | The United States, the Amazon | 一部の国名・川・山など |
| 形容詞+the(集団を表す) | The rich, the elderly | 特定のグループ |
| 楽器や発明品を語るとき |
I play the piano. He invented the telephone. |
カテゴリとしての代表 |
theの使い方は最初はなかなかイメージを掴むのが難しいかもしれません。
正直これは英文を多読したり実際の英会話で使って慣れていくしかありません。
ちなみに僕は
”the”は「これだよね?」って相手と共有するための単語
という意識を持ちながら英文を読んだり実際の英会話で練習をしています。
つまり英語を読むときも話すときも、
「この名詞って特定されてるんだっけ?」
と意識しながら行うんですね。
最初は時間がかかるかもしれませんが数をこなすことで自然に使えるようになっていきます。
ぜひこれを意識してみてください。
冠詞をつけないパターン
英語の名詞には冠詞をつけないパターンもあります。
いわゆる
”無冠詞”
の場合ですね。
主なものはこの7パターンになります。
① 不可算名詞で特定されていないとき
② 複数形の名詞を一般的に言うとき
③ 食事・曜日・月・季節など
④ 言語名・学問名・スポーツ名
⑤ 交通手段や通信手段
⑥ 特定の施設名を“本来の目的”で使うとき
⑦ 抽象的な概念
ちょっとややこしいのでそれぞれ例文で解説していきますね。
無冠詞のパターン① 不可算名詞で特定されていないとき
これは先ほども説明しましたが
”数えられない名詞でなおかつ特定されていないとき”
ですね。
I like music.
(私は音楽が好き)
musicは不可算名詞です。
そして無冠詞なのでこの場合は
”特定されていない音楽、つまり音楽なら何でも好き”
なんですね。
だからニュアンスは
「音楽というジャンル全体が好き」
というイメージになります。
ちなみにこの文に定冠詞theをつけてみましょう。
theは特定されていて可算名詞でも不可算名詞でも使えるというルールでしたよね。
I like the music.
(私はその音楽が好き)
この場合は、
「特定のその音楽が好き」
というニュアンスになります。
ちなみにこの文ではa/anは間違いなのは分かりますか?
(誤)I like a music.
理由はmusicは数えられない名詞(不可算名詞)だからです。
a/anは不可算名詞では使えません。
無冠詞のパターン② 複数形の名詞を一般的に言うとき
英語では
”複数形の名詞を一般的に言うときは冠詞(a / an / the)をつけずに「無冠詞」で使う”
というルールがあります。
おそらく・・
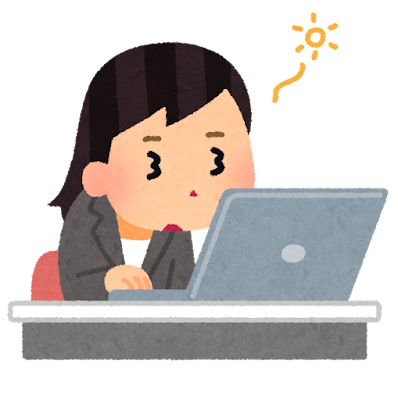
何のこと???
と思っていると思うので詳しくみていきましょう。
これは
”複数形の名詞で「世の中全体のこと」「一般論」を話すとき”
ということです。
例文をみてみましょう。
Cats are cute.
(猫はかわいい。)
これは猫という生き物(全ての猫)が可愛いというイメージですね。

猫ってみんな可愛いよね~♡
みたいなニュアンスで話す感じです。
Books are expensive.
(本は高い)
これは本というもの全体が高いというイメージですね。

本ってどれも高いよね~
みたいなニュアンスで話す感じです。
Teachers work hard.
(教師は一生懸命働く。)
これは教師という職業全体が一生懸命働くというイメージですね。

教師という職業の人ってみんな一生懸命働いているよね
みたいなニュアンスで話す感じです。
People need love.
(人は愛が必要だ。)
これは”人間全体”を指す一般論というイメージですね。

人間って基本愛が必要だよね
みたいなニュアンスで話す感じです。
分かりにくければ
無冠詞の複数形は「○○という存在全体」を指す
という認識でOKです。
無冠詞のパターン③ 食事・曜日・月・季節など
英語では
”食事・曜日・月・季節など は基本的に冠詞をつけなくてもOK”
です。(ただし例外もあります)
食事(breakfast / lunch / dinner)
一般的に
「食事をした」
ということが言いたいときは冠詞はつけなくてもOKです。
I had breakfast at 7.
(7時に朝食をとった。)
We usually eat dinner at home.
(夕食はいつも家で食べます。)
ただし
”その食事が特定されていたり形容詞がつく場合は(the/a)が必要”
になります。
The dinner we had last night was amazing.
(昨晩食べた夕食は素晴らしかった)
これは
「昨晩食べた夕食」
ということで夕食が特定されていますね。
だからこの場合は例外としてtheが必要となります。
I feel sick after eating a bad breakfast.
(まずい朝食を食べて気分が悪い。)
これは
「まずい朝食」
ということで朝食の前にbadという形容詞がついています。
食事の前に形容詞ががつく場合はaが必要となります。
aは不定冠詞なのでこの時点ではまだ”そのまずい朝食”は特定されていません。
つまり
”どんなまずい朝食でも当てはまる一つのまずい朝食”
というニュアンスです。
ちなみにこの場合はtheでも文法的にはOKですがニュアンスが少々異なります。
I feel sick after eating the bad breakfast.
(そのまずい朝食を食べて気分が悪い。)
この文でtheを使う場合のニュアンスは、
「先ほどの話に出たそのまずい朝食」
という感じですね。

さっき話したホテルの朝食まずかったよね~
みたいなイメージです。
曜日(Monday / Friday など)
月(January / March など)
季節(spring / summer / fall / winter)
といったカレンダー通りのことを言いたいときは冠詞はつけなくてもOKです。(これも例外があります)
I’ll see you on Monday.
(月曜日に会いましょう。)
Friday is my favorite day.
(金曜日が好きです。)
My birthday is in March.
(私の誕生日は3月です。)
School starts in September.
(学校は9月に始まります。)
I love spring.
(春が大好き。)
We go skiing in winter.
(冬にスキーに行きます。)
ただしこれも例外があって、
曜日・月・季節が”思い出”とか”特別な何かとセット”なら ”the” が必要
というルールがあるんですね。
つまりこんな感じで曜日や月や季節が特定されたものとセットということです。
I remember the Monday after the festival.
(祭りの翌週のあの月曜日を思い出します。)⇒「祭りの翌週のあの月曜日」なので特定されている
The March I visited Paris was cold.
(私がパリを訪れた3月は寒かった。)
⇒「パリを訪れた3月」なので特定されている
I’ll never forget the summer we met.
(私たちが出会ったあの夏を私は決して忘れません。)
⇒「私たちが出会った夏」なので思い出として特定されている
覚え方としては、
「カレンダー通り」や「いつものこと」は無冠詞
「思い出」「特別な何かとセット」なら the が必要
という認識でいいでしょう。
無冠詞のパターン④ 言語名・学問名・スポーツ名
英語では
”言語名・学問名・スポーツは基本的に冠詞をつけなくてもOK”
です。(ただしこれも例外もあります)
① 言語名
I can speak English.
(英語が話せます。)
She studies Japanese at university.
(大学で日本語を勉強しています。)
Do you know French?
(フランス語、わかりますか?)
② 学問名
He loves math.
(彼は数学が好き。)
I majored in history.
(私は歴史を専攻しました。)
We have science class today.
(今日は理科の授業があります。)
③ スポーツ名
I play soccer.
(サッカーをします。)
She is good at tennis.
(彼女はテニスが得意。)
Do you like basketball?
(バスケ好き?)
スポーツ名は不可算名詞として扱われるので冠詞は不要です。
ただしこれも例外があって、
学問や言語を特定の内容や種類として説明するときは the / a をつける
必要があるんですね。
theが付く場合(特定のもの・修飾語あり)
The English spoken in Ireland is different.
(アイルランドで話されている英語は違います。)
⇒「アイルランドで話されている英語」ということで特定されているからtheが必要
a がつく場合(種類・ひとつの例を言うとき)「a + 形容詞 + 名詞」の形で「1つの何か」
Chemistry is a fascinating science.
(化学は魅力的な科学のひとつ。)
⇒化学が数ある科学の種類の中の“1つの分野として認識され可算名詞化するためaが必要
覚え方としては、
学問を「ジャンル全体、一般的なものとして話す」ときは無冠詞
学問を「特定の内容や種類として説明する」ときは the / a が必要
という認識でいいでしょう。
無冠詞のパターン⑤ 交通手段や通信手段
英語では
”交通や通信手段を表すとき、特定しない手段全体を表す場合は基本的に冠詞をつけなくてもOK”
です。(これも例外があります)
「車で行きます」
「電車で来ました」
「メールでやりとりしましょう」
みたいな交通手段や通信手段を場合のことですね。
英語では
by + 交通/通信手段名
で(~で)という表現になります。
I go to work by train.
(電車で通勤しています。)
She came by car.
(彼女は車で来ました。)
We traveled by bus.
(バスで旅行しました。)
Please contact me by email.
(メールで連絡してください。)
He told me the news by phone.
(彼は電話で知らせてくれた。)
ただこのようにあくまで手段として表現するだけなら冠詞は不要なんですが、
”交通機関や通信手段を具体的な特定のものとして表すときは冠詞が必要”
となります。
I took a bus to the station.
(私はバスに乗って駅まで行きました)
⇒「1台のバスに乗って駅まで行った」 のでa が必要
He sent an email to his boss.
(彼は上司に1通のメールを送った)
⇒「上司に送った1通のメール」なのでan が必要
She is on the phone right now.
(彼女は今電話中です)
⇒「(今)電話中」といった特定の動作なので the を使う
"on the phone"で電話中といった意味があります。これはこのまま丸暗記してしまってもいいでしょう。
覚え方としては、
交通や通信を「手段として使う」ときは無冠詞
交通や通信を「具体的な特定のものとして使う」ときは冠詞が必要
という認識でいいでしょう。
無冠詞のパターン⑥ 特定の施設名を“本来の目的”で使うとき
英語では
”特定の施設名(school, hospital, church, prison, bedなど)を“本来の目的”で使うとき冠詞をつけなくてもOK”
です。(これも例外があります)
これはちょっとややこしいので表にまとめてみました。
| 主な施設 | 本来の目的 | 例文 |
| school(学校) | 学ぶため | She is at school. |
| hospital(病院) | 治療・入院のため | He is in hospital. |
| church(教会) | 礼拝するため | They go to church on Sundays. |
| prison(刑務所) | 刑を受けるため | He was sent to prison. |
| bed(ベッド) | 寝るため | I went to bed early. |
つまり施設を
”本来の目的=「役割・機能」として使うニュアンスで話すときは無冠詞でOK”
ということですね。
ただこの場合、
冠詞をつけるとニュアンスがかなり異なってくるため注意が必要です。
この2つの例文をみてみましょう。
① He is in hospital.
② He is in the hospital.
それぞれ冠詞がついているかついていないかの違いですが聞き手からするとこの2つのニュアンスはかなり違ってきます。
まず①の例文ですが日本語訳はこうなります。
He is in hospital.
(彼は入院している)
冠詞をつけない場合は施設の本来の機能や役割といったニュアンスでしたよね。
だからこの場合は
「病院の中にいる」つまり入院して治療を受けている
というニュアンスになるんです。
それに対して②の例文はどうでしょうか?
He is in the hospital.
(彼はその病院の中にいる)
冠詞をつける場合は
「病院という建物にいるけど治療目的とは限らない、つまり、”その病院という“場所”にいることが大事」
というニュアンスになるんですね。
病院の中にいる人は治療目的(本来の機能)の人ばかりではありません。
お見舞いの人もいますし病院で働く医師や看護師だっていますね。
こういった病院内で働く人や目的が不明な人を言いたいときは冠詞が必要となります。
I met her at the hospital.
(病院で彼女に会った)⇒見舞いや仕事など、用事で行った可能性(目的が不明)
He works at the hospital.
(彼は病院で働いている。)⇒医者や看護師など病院で働くスタッフ(そこで働くスタッフ)
She was waiting in the hospital lobby.
(病院のロビーで待っていた。)⇒中にいたけど入院や治療ではない可能性(目的が不明)
覚え方としては、
施設を「その施設の“本来の目的”で使ってる」ときは無冠詞
施設を「“場所”として存在していることに注目されている」ときは冠詞が必要
という認識でいいでしょう。
無冠詞のパターン⑦ 抽象的な概念
抽象的な概念とは
”愛・自由・幸福・正義・平和など、人間の感情や思想、状態を表す言葉”
のことをいいます。
英語では
”このような抽象的な言葉には冠詞をつけなくてもOK”
です。(ただしこれも例外もあります)
これらの言葉は、広い意味をもつ“概念だから数えられないし特定もできない、だから基本的には無冠詞でOKなんですね。
Love is important.
(愛は大切だ。)
Freedom is a basic human right.
(自由は基本的人権だ。)
Happiness cannot be bought.
(幸福はお金で買えない。)
Justice must be served.
(正義は守られなければならない。)
Education opens doors.
(教育は可能性を広げる。)
しかしこれも例外があって
”抽象名詞でも、「特定された」「具体的な種類として語る」ときは、a / the が必要”
となります。
This is a love I’ve never felt before.
(これは私が今まで感じたことのない愛です。)
⇒「今まで感じたことのない1つの特別な愛」なので具体的で数えられるからaが必要
The freedom you enjoy today came with a cost.
(あなたが今日享受している自由には、代償が伴いました。)
⇒「今あなたが享受している自由」なので特定されているからtheが必要
That was a happiness I’ll never forget.
(それは一生忘れられない幸せでした)
⇒「ある出来事で感じた1つの幸せ」といった1つの例なのでaが必要
覚え方としては、
抽象名詞を「”一般的な話”で使ってる」ときは無冠詞
抽象名詞を「”具体的な例や特定の話”で使っている」ときは冠詞が必要
という認識でいいでしょう。
英語初心者が”a/an”と”the”と”無冠詞”の使い分けが一発で分かる方法

ここまで冠詞の説明をしてきましたが正直、
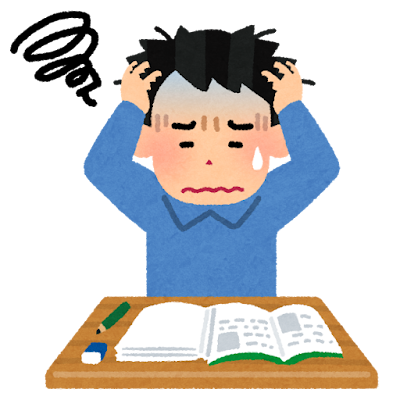
ややこしすぎる そんなに使い分け覚えられねーよ!!
という人がほとんどだと思います。
僕も偉そうに言ってますが100%完全に使いこなせているかと言われるとかなり微妙です(笑)
なぜなら冠詞という概念は日本語にはないからなんですね。
ちなみに日常英会話では冠詞(a/an/the)をつけ忘れても基本通じることが多いです。
ただし上記のようにニュアンスが異なってきますしそもそも冠詞を使うべきとこで使っていないとネィティブからすればすごく不自然な英語に聞こえるらしいです。
冠詞を使うべきところで使っていないとネィティブからすれば、

This person is a beginner in English.(この人英語初心者なんだなぁ・・)
と思われるでしょう。
ちなみにネィティブは会話をするときに冠詞(a/an/the)はハッキリと発音するみたいです。
だからたった一単語だけですがちゃんと発音しないと、
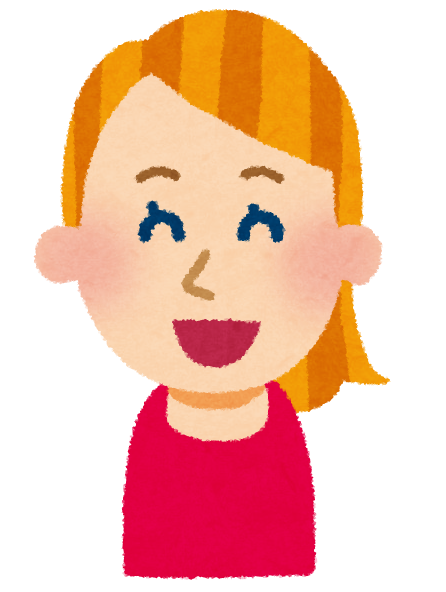
He didn't say "the" just now.(この人今”the"を言わなかったな)
こんな感じでハッキリと分かります。
英語初心者のままでいいならそれでもいいと思うんですが、これでは
”英語ができるカッコイイ大人”
とは言えないですよね(笑)
だから英語ができるカッコイイ大人になりたければ冠詞は決しておろそかにできません。
しかしそうはいっても、
”冠詞(a/an/the)と無冠詞の使い分け”
は僕たち日本人の頭を悩ませるところです。
そこでここでは
「英語初心者でも”冠詞(a/an/the)と無冠詞の使い分け”が一発で分かる方法」
を解説します。
おススメのやり方はある名詞が出てきたら以下のフローチャートで確認していきます。
①「それは1つだけなの?数えられるの?」
→YES → ②へ
→ NO(複数・数えられない)→ 無冠詞 or the
②「聞き手はどれのことか分かってる?(初登場なの?)」
→ YES → the
→ NO → a / an
これをもっと分かりやすく図にまとめるとこんな感じです。
| 話し手と聞き手の関係 | 単数 | 複数・不可算 |
| お互い分かっていない(初登場) | a / an | 無冠詞 |
| お互い「どれのことか」分かっている | the | the |
これを理解した上で一度下記の問題をやってみて下さい。
空欄には冠詞(a/an/the)のいずれかが入ります。無冠詞の場合もありますのでその場合は空欄でOKです。
1. I saw ___ elephant at the zoo.
2. He is reading ___ book about history.
3. ___ sun rises in the east.
4. She goes to work by ___ bus.
5. I love ___ music.
6. We had ___ lunch at noon.
7. Look at ___ stars in the sky!
8. I want to buy ___ car.
9. ___ moon was beautiful last night.
10. She is in ___ hospital after the accident.
・
・
・
・
どうでしょうか?
ちなみに正解はこのようになります。
空欄には冠詞(a/an/the)のいずれかが入ります。無冠詞の場合もありますのでその場合は空欄でOKです。
1. I saw an elephant at the zoo.
(私は動物園で象を見た)
⇒初めて出てくる象なので「a/an」使用
2. He is reading a book about history.
(彼は歴史についての本を読んでいる)
⇒この文では「どの本か」はまだ分かっていない=はじめて出てきているので不特定 → a book
the にするなら「the book you gave me」のように特定される必要あり。
3. The sun rises in the east.
(太陽は東から昇る)
⇒「the sun」は唯一の存在(世界に1つ)=特定 → the
4. She goes to work by 無 bus.
(彼女はバスで仕事に行きます)
⇒「by + 交通手段」の形は冠詞なし → by bus / by train / by car
5. I love 無 music.
(私は音楽が好き)
⇒「music」は不可算名詞で、抽象的・一般論 → 無冠詞
6. We had 無 lunch at noon.
(私たちは正午に昼食を食べました)
⇒「lunch / breakfast / dinner」などは一般的な食事として言うときは無冠詞
特定したり形容詞つくと「the lunch / a nice lunch」になる
7. Look at the stars in the sky!
(空の星を見て)
⇒「空の星たち」=空にある特定の星々(複数系) → the
8. I want to buy a car.
(私は車を買いたい)
⇒「車を1台買いたい」→ 不特定の1台(車ならなんでもいい) → a
9. The moon was beautiful last night.
(月が綺麗な夜だった)
「the moon」=世界で1つしかない → the
10. She is in 無 hospital after the accident.
(彼女は事故のあと病院に入院している)
⇒入院・治療の目的で病院にいる→無冠詞
※アメリカ英語だと「the hospital」でもOK
いかがだったでしょうか?
できなかったとしても落ち込む必要はありません。
こういった練習を何度も繰り返していくことで頭の中でいちいち考えなくても感覚で分かるようになります。
ただここで重要なポイントは
「なぜそうなるのか?を常に考えること」
です。
例えば・・
I want to buy a car.
(私は車を買いたい)
であれば
「なぜaが入るのか?theや無冠詞でもいけそうな気がするけどなぜダメなのか?」
を人に説明できるまで頭に叩き込むことですね。
最初は非常に面倒くさいと思うかもしれませんが英語はこういった
「なぜそうなるのか?」
を何度も繰り返すことで分かるようになってくるものです。
慣れてくればいちいち頭で考えなくても感覚で分かるようになってきます。
だからとにかく何度も「なぜ?」を繰り返して反復練習するしかないんですね。











