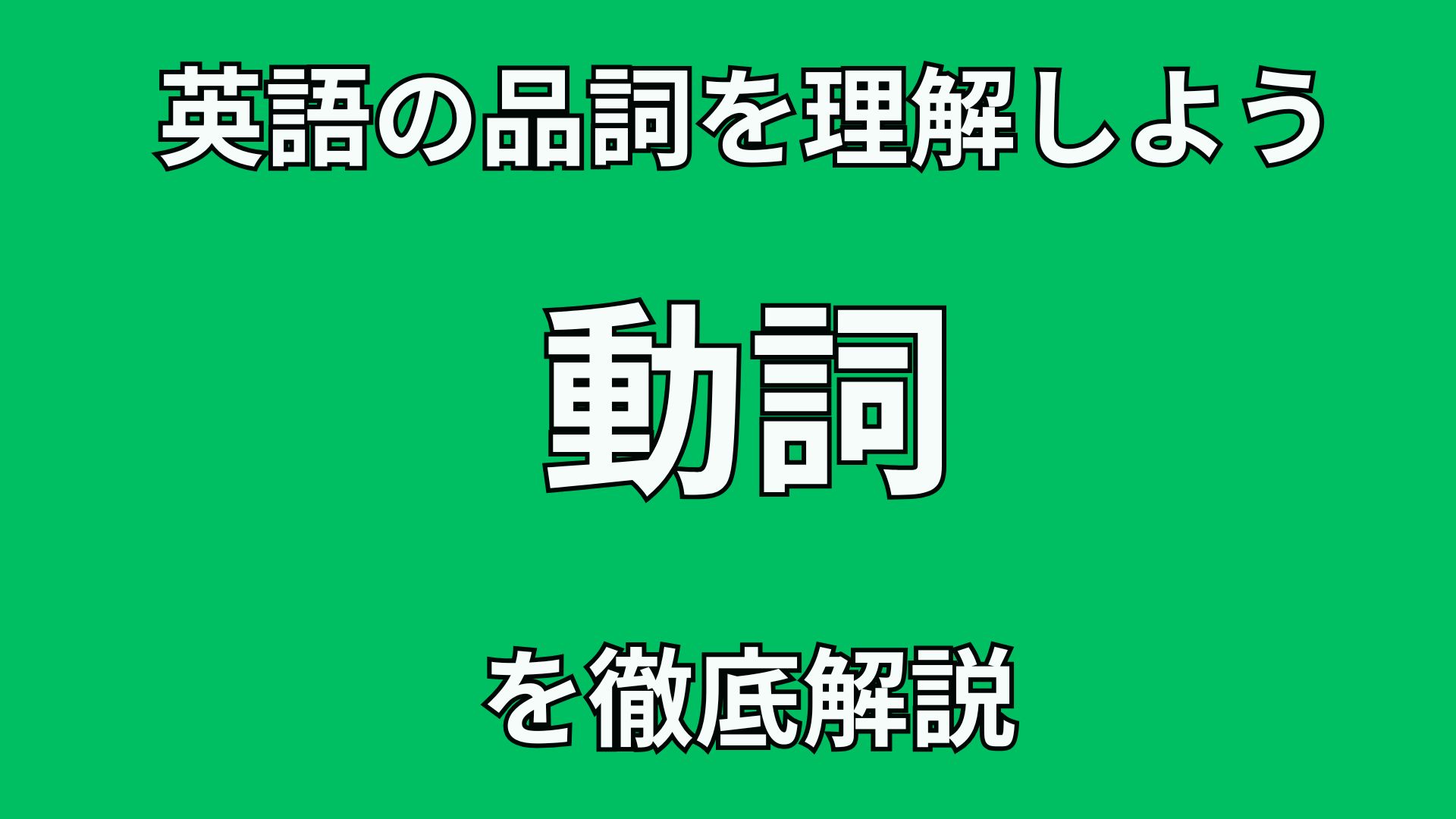
英語の動詞とは?

動詞(verb)を一言でまとめると以下のとおりです。
動詞は「動作」や「状態」を表し、文の中心(述語)となる語です。
英語の文は、基本的に
”主語(誰が)+”動詞(何をする)”
の形で成り立ちます。
これはどんな難しい英文でも例外はありません。そういうルールなんです。
英語の文では、動詞がなければ文が成り立ちません。
英語の動詞はそれくらい重要な品詞なのでここでしっかりと理解しておきましょう。
英語の動詞の文法的役割とは?

英語の動詞は文の中で以下のような文法的役割を持ちます。
① 文を成立させる中核(述語)になる
② 文の構造の決定
③ 時制・態・法を決める
④ 助動詞や補助動詞と組み合わせることでより複雑な意味を作る
英文法をやったことのない人にとってはこれを見るだけで、
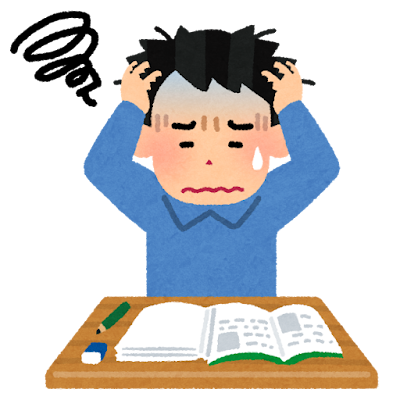
うわっ!! ダル・・・
となるかもしれませんね(笑)
しかし英語では動詞を理解していないとそのあとの英文解釈がチンプンカンプンになります。
できるだけ分かりやすく解説しますのでこの機会に必ず理解しておきましょう。
動詞の文法的役割① 文を成立させる中核(述語)になる
最初に述べたとおり
”英語の文では必ず動詞がある”
ということを念頭に置いておいて下さい。
ちなみに”述語”ってご存知ですか?
主語・述語、それぞれ小学校の国語で習うのですがそれを説明しろといわれてもなかなかできないと思うんですよね。
本題に入る前にまず主語・述語について押さえておきましょう。
シンプルにまとめるとこんな感じです。
主語・・”誰が・何が”を表す
述語・・”どうした・どうであるか”を表す
英語の文は基本的に主語 (S) + 動詞(述”)(V) で構成されます。
例文はこんな感じですね。
She runs.(彼女は走る)
この場合の(誰が?)にあたる主語はShe(彼女)ですよね。
ではShe(彼女)はどうしたのでしょうか?
ここで(どうした?)にあたる述語がruns(走る)という動詞になっています。
つまり動詞は
”主語が何をしたのか?”
という部分を明確にしているんですね。
英語では主語だけでは文になりません。
She・・・(彼女は・・)
これだけでは”Sheがどうしたのか?”分かりませんし文として成り立たないわけです。
また日本語では主語と述語は別に言わなくても意味が伝わったりするし文法上間違いはないんです。
例えばですがこのような文があったとしましょう。
私はディズニーランドに行きます。
でも例えば”私”という主語を省略して
ディズニーランドに行きます。
と表現しても文としては成立しますよね。
英語はこのルールが基本的に成立しないということ。(例外はあります)
この文であれば・・
I go to Disneyland.
と主語(I)と動詞(述語)(go)の両方がなければならないのです。
ただ英語でも主語が省略されることは例外的にあります(命令文など)
ただその場合文の意味がまったく異なってくるんですね。
この文で主語(I)をなくすとこのようになります。
Go to Disneyland.(ディズニーランドに行きなさい)
どうですか?
意味が全然違いますよね(笑)
この場合、
”私はディズニーランドに行く”
ということを相手に伝えたいのに
”ディズニーランドに行きなさい”
と相手に命令しちゃってますね(笑)
主語を言うか言わないだけで英語ではこんなに意味が変わってくるんです。
英語では基本的に
”主語 (S) + 動詞(述語)(V)”
のかたちをとるという認識でOKです。
ちなみに英語では動詞(述語)が省略されることは絶対にありません。
どんな難しい文でも英語では動詞にあたるものが必ずあると理解しておきましょう。
動詞の文法的役割② 文の構造の決定
英語では動詞の種類によって後ろに続く語句(目的語や補語など)が異なってきます。
あとで詳しく説明しますが英語の動詞には様々な種類があります。
使い分ける動詞によって文の構造自体が変わってくるんですね。

動詞で文の構造が変わるってどういうこと?
と思っている人も多いでしょう。
ここでは英語の基本5文型を理解しておく必要があります。
英語の基本5文型については関連記事で詳しく解説していますのでこちらをご覧ください。
※関連記事
英語の”基本5文型”を40代英語初心者でも分かるように徹底解説
基本5文型については上記の記事で詳しく解説しているためここでは説明は割愛しますがまとめるとこんな感じです。
| 文型 | 内容 | 例文 |
|
第1文型 (S+V) |
主語+動詞 | The sun shines.(太陽が輝いている) |
|
第2文型 (S+V+C) |
主語+動詞+補語 | She is happy.(彼女は幸せです) |
|
第3文型 (S+V+O) |
主語+動詞+目的語 | I read books.(私は本を読みます) |
|
第4文型 (S+V+O+O) |
主語+動詞+人+物 | He gave me a gift.(彼は私に贈り物をくれました) |
|
第5文型 (S+V+O+C) |
主語+動詞+目的語+補語 | We made him happy.(私たちは彼を幸せにしました) |
見れば分かると思うんですがどの文型も動詞は必ずありますよね。
英文は全てこの5文型のルールに則って文が構築されているんですが動詞の種類によって動詞の直後におけるものが違ってきます。
つまり英語の動詞は文の構造全体を支配するということ。
これは英文法を学ぶ上でめちゃくちゃ重要ですので覚えておきましょう。
以上これが動詞の種類によって文の構造が変わるということですね。
動詞の文法的役割③ 時制・態・法を決める
英語の動詞は
その文の”時制・態・法”
を決定します。
これも文を構築する上で重要な要素となるんですが何のことか分からないと思うのでそれぞれ解説していきますね。
英語の”時制・態・法”をまとめるとこんな感じです。
・時制・・現在・過去・未来を表す
・態・・受動態か能動態かを表す
・法・・事実なのか仮定なのか命令なのかを表す
英語の”時制”とは?
時制とは
”その文が現在なのか?過去なのか?未来なのか?といった時間区分のこと”
をいいます。
例えば以下の例文でそれぞれみていきましょう。
私はハンバーガーを食べる
この文を現在・過去・未来の時間区分で表現するとこのようになります。
現在形:I eat a hamburger.
(私はハンバーガーを食べる)
過去形:I ate a hamburger.
(私はハンバーガーを食べた)
未来形:I will eat a hamburger.
(私はハンバーガーを食べるつもりだ)
過去形・未来形においてはそれぞれeatという動詞が変化しているのが分かりますか?
過去形においてはeatの過去形であるateが、そして未来形においてはeatの直前に未来形を表現するwillをおいていますね(will+動詞の原形で~するつもり)。
英語では
”動詞を変化させたり直前に助動詞(willなど)をおくことでその分の時間区分を変化させることができる”
ということです。
英語の時制表現については関連記事でもっと詳しく解説していますのでこちらをご覧ください。
※関連記事
英語の”過去形”を40代英語初心者でも分かるように徹底解説
英語の”未来形”を40代英語初心者でも分かるように徹底解説
英語の”態”とは?
英語の態は”能動態”と”受動態”に対応する文の構造のことをいいます。
2つの態の違いをまとめるとこんな感じです。
能動態・・”主語が動作を表す形”
受動態・・”主語が動作を受ける形”
英語の態は動詞を変化させることで表現することが可能です。時制と同じですね。
例えばこの2つの文なんですが意味的にはほとんど一緒です。
(能動態)She wrote a letter.
(彼女が手紙を書いた)
(受動態)A letter was written by her.
(手紙が彼女によって書かれた)
能動態と受動態の違いは、
”話し手からして伝えたい集点があたるのが主語なのか動作の対象なのか”
ということです。
まずは能動態の文からみてみましょう。
She wrote a letter.(彼女が手紙を書いた)
これは”She(主語)”・”wrote(writeの過去形)(動詞)”・”a letter(目的語)”となっています。
この文の集点は主語(彼女)にあるというのが分かりますか?
つまりこの文の主役はあくまで(彼女)なんです。
だから話し手からすればこの文で伝えたいイメージは・・・
「彼女が手紙を書いたことを相手に伝えたい」
とうこと。
ちなみに一般的な文の場合は能動態の形をとっています。
続いて受動態の文も見てみましょう。
A letter was written by her.
(手紙が彼女によって書かれた)
先ほどと違って話の集点は主語(手紙)にあるというのが分かりますか?
つまりこの文の主役はあくまで(手紙)なんです。
だから話し手からすればこの文で伝えたいイメージは・・・
「その手紙が彼女に書かれたことを相手に伝えたい」
ということ。
このように英語の受動態は
”受け手を強調したいとき”
によく使用されます。
英語の受動態は”be動詞+過去分詞”+(by動作主)で表現できます。
The cat was chased by the dog.
(その猫が犬に追いかけられた)
The cake was eaten by Tom.
(そのケーキはトムによって食べられた)
動詞を確認することでその文が受動態なのか能動態なのか見分けることが可能になります。
過去分詞やbe動詞について分からない人はこちらの関連記事で詳しく解説しています。
※関連記事
英語の”分詞”って何?40代英語初心者でも分かるように徹底解説
英語の”be動詞”って何?40代英語初心者でも分かるように徹底解説
英語の”法”とは?
英語の文法における”法”とは、
”動詞が話し手の意図や態度をどのように表すかを示す文法の仕組み”
のことをいいます。
ちょっと複雑ですが、日本語で言えば
「〜だろう」「〜してほしい」「〜せよ」などのニュアンス
に当たります。
英語には主に以下の 3つの基本的な法があります
直接法・・事実・現実を表現する
命令法・・命令・依頼を表現する
仮定法・・非現実・願望を表現する
まずは直接法の文からみてみましょう。ちなみに英文の大半はこのような直接法の形です。
She is tired.
(彼女は疲れている)
He goes to school every day.
(彼は毎日学校に行く)
上記の文では”疲れている”や”学校に行く”という事実や現実を表現していますね。
続いて命令法の文です。
Sit down.
(座りなさい)
Please open the window.
(窓を開けてください)
英語における命令法は
”(~してほしい ~しなさい)という動詞の原形を文頭におき、主語(you)を省略する形”
になります。
命令法はすべて相手(you)に対して言っていますが、文の中では”you”は省略するのが普通です。
また文頭にPleaseをつけることで少し丁寧な言い回しでの表現になります。
最後に仮定法の文です。
If I were you, I’d apologize.
(もし私があなただったら謝ります)
英語における仮定法とは、
”現実ではないこと(もし〜なら)や願望・提案・必要性を表す形”
となります。
文法的に少し難しいですが日常英会話でもけっこう出てくる重要な表現です。
上記の英文では
”もし私があなたなら~”
という現実ではないことを提案していますよね。
英語の仮定法はこのように、
”現実とは違う想像”や”ありえたかもしれない過去”などを表す特別な文法表現となります。
仮定法はちょっとややこしい単元なので別記事で詳しく解説していますのでこちらもご覧ください。
※関連記事
英語の”仮定法”って何?40代英語初心者でも分かるように徹底解説
動詞の文法的役割④ 助動詞や補助動詞と組み合わせることでより複雑な意味を作る
英語の動詞はそれ単体で使用されるだけでなく、
助動詞(can, will, must など)やbe動詞・have・do などの補助動詞と組み合わさることで、
より複雑な意味を作ります。
これらの組み合わせをまとめるとこんな感じです。
・助動詞との組み合わせ
・be動詞(補助動詞)との組み合わせ
・have(補助動詞)との組み合わせ
・do(補助動詞)との組み合わせ
ちなみに助動詞と補助動詞の違いは以下のとおりとなります。
助動詞・・話し手の気持ちや判断を表すための動詞(can・will・mayなど)
補助動詞・・文法的な機能を助けるための動詞(be動詞・have・doの3種類のみ)
分かりやすくいうと、
”補助動詞はそれ単体では意味を持たず文法上必要なもの”
”助動詞はそれ単体で意味を持ち動詞に気持ちを付け加えるもの”
という認識でいいかと思います。
助動詞との組み合わせ
英語の助動詞は動詞に意味的なニュアンスを加える品詞です。
「できる」「すべき」「かもしれない」「するつもり」など、
話し手の態度や気持ちを表現します。
助動詞は通常は動詞の前におかれてこれらのニュアンスを表現することが可能です。
主な助動詞は以下のとおりです。
| 助動詞 | 意味 | 例文 |
| can / could | 可能・能力 | I can swim.(私は泳げる) |
| will / would | 意志・未来・丁寧 | I will go.(私は行くつもりだ) |
| must | 義務・強い推量 | You must study.(あなたは勉強しなければならない) |
| should | アドバイス・義務 | You should sleep early.(あなたは早く寝た方がいい) |
| may / might | 許可・可能性 | He may come.(彼は来るかもしれない |
なお文法上のルールとしてこれらの助動詞を使用した場合はその後にくる動詞は必ず”原型”となります。
助動詞と動詞の原形ついては別記事で詳しく解説していますのでそちらをご覧ください。
be動詞(補助動詞)との組み合わせ
動詞の前にbe動詞(am, is, are, was, were)を補助的に使うと、以下のような表現が可能になります
①進行形(主語+be動詞+動詞ing(現在分詞))
She is reading a book
(彼女は読書中です)
進行形は”今~をしている”という表現になります。
②受動態(主語+be動詞+過去分詞)
The cake was eaten.
(そのケーキは食べられた)
受動態については先ほど解説したとおりですね。
主語に集点をおいて(~された)という表現が受動態となります。
be動詞及び進行形については別記事で詳しく解説していますのでそちらをご覧ください。どちらもめちゃくちゃ重要な文法要素ですのでしっかり理解しておきましょう。
※関連記事
英語の”分詞”って何?40代英語初心者でも分かるように徹底解説
英語の”be動詞”って何?40代英語初心者でも分かるように徹底解説
have(補助動詞)との組み合わせ
動詞の前にhave(has)を使うと、完了・経験・継続などのニュアンスが表現できます。
これは”完了形”と呼ばれます。
完了形は
主語+have(has)+過去分詞
で表現できます。
例文をみてみましょう。
(完了)I have finished my homework.
(私は宿題を終えた)
(経験)She has visited Paris.
(彼女はパリに行ったことがある)
(継続)We have lived here for 5 years.
(私たちは5年間パリに(継続して)住んでいる)
この3つのニュアンスで文を表現したいときは現在完了形で文を作ります。
完了形ついては別記事で詳しく解説していますのでそちらをご覧ください。英会話で超頻出ですので理解しておくと会話の幅がめちゃくちゃ広がります。
※関連記事
英語の”完了形”って何?40代英語初心者でも分かるように徹底解説
do(補助動詞)との組み合わせ
do(does)は否定文や疑問文を作るときに使われる補助動詞です。
①否定文(主語+do(does/did)+not+動詞の原形)
I do not like coffee.
(私はコーヒーは好きではない)
He did not go to school.
(彼は学校に行かなかった)
否定文は”~しない・~しなかった”という表現です。
(動詞~する)の前にdo not/did not/does notをつけることで(動詞~しない ・しなかった)という否定文が作れます。
②疑問文(Do / Does / Did + 主語+動詞の原形?)
Do you like sushi?
(あなたは寿司は好きですか?)
Did she call you?
(彼女はあなたに電話しましたか?)
疑問文は”~ですか?・~でしたか?”という表現です。
文頭にDo/Does/Didをおき、その直後に主語と動詞の原形を入れることで(主語は~しますか?・しましたか?)という疑問文が作れます。
英語の疑問文及び否定文ついては中一で習う英文法の超基礎です。
分からない方は別記事で詳しく解説していますのでそちらをご覧ください。
※関連記事
英語の”疑問文”の作り方?40代英語初心者でも分かるように徹底解説
英語の”否定文”の作り方?40代英語初心者でも分かるように徹底解説
英語の動詞の種類とは?

英語の動詞は性質や働きによっていくつかの種類に分類されます。
ここでは英語習得に必要不可欠な主要な種類をわかりやすくまとめて解説します。
まず英語の動詞ですが大きくわけて以下4つに分類されます。
・be動詞
・一般動詞
・補助動詞
・助動詞
なお補助動詞・助動詞については別記事で詳しく解説していますのでここでは説明は割愛させていただきます。
ではbe動詞と一般動詞について、またその使い分けについてそれぞれ解説していきますね。
英語の動詞の種類 be動詞
be動詞は
「〜である」「〜にいる」
といった、存在や状態を表す動詞です。
具体的にはisとかareのことですね。
主語が何であるか、どこにいるか、どんな状態かを説明する際に使います。
be動詞の特徴は
”必ず主語と補語がイコールである”
という点がポイントです。
be動詞を使った例文をみてみましょう。
She is a teacher.(彼女は先生です)
He is not tired.(彼は疲れていません)
上記の分はそれぞれ主語が(何か?)(どんな状態か?)ということを説明していますよね。
では同じくbe動詞を使った次の例文はどうでしょうか?
I am studying English.
(私は英語を勉強しています)
They are watching TV.
(彼らはテレビを見ています)
This book is written in English.
(この本は英語で書かれています)
The house has been sold.
(その家は売られました)
それぞれ現在分詞・過去分詞・完了形が入って文の構造が変わって難しく感じるかもしれませんが(主語=補語)の理屈は同じです。
それぞれ主語がどんな状態かを表現しているのが分かりますよね。
つまりbe動詞の文は主語の状態(補語)を説明するわけですから当然、主語=補語とならなければいけないんです。
ちなみにこれは基本五文型でいえば第二文型(S+V+C)にあたります。
第二文型はS(主語)=C(補語)が基本でありVの部分にはよくこのbe動詞が使われます。
be動詞は
”主語が何であるか?時制がどうか?”
ということで以下のように様々な形に変化します。
| 主語(使用用途) | 時制 | be動詞の形 |
|
to不定詞で使うことが多い |
原形 | be |
| I | 現在形 | am |
| he, she, it | 現在形 | is |
| you, we, they | 現在形 | are |
| I, he, she, it | 過去形 | was |
| you, we, they | 過去形 | were |
| 受動態・完了形を作る | 過去分詞 | been |
| 進行形を作る | 現在分詞 | being |
ちなみにこの表は
”めちゃくちゃ重要で英語を学ぶ上で知らなければお話にならないレベル”
なので意味は分からなくてもとりあえずこの機会に丸暗記して覚えてほしいと思います。
なおbe動詞というのはその名のとおりbeという動詞が時制や主語に合わせて変化しているだけで、複数あるように思えますが実質的にbe動詞はbeの一つのみです。
be動詞についてまだよく分からない人は別記事でさらに詳しく解説していますのでそちらをご覧ください。
※関連記事
英語の”be動詞”って何?40代英語初心者でも分かるように徹底解説
英語の動詞の種類 一般動詞
一般動詞は
「食べる」「行く」「知っている」「働く」など、
主語の行動や状態を表す基本の動詞です。
英語ではbe動詞・助動詞・補助動詞以外の動詞はすべて一般動詞と呼ばれます。
英語の一般動詞は数が無数にあり、主語の動作や状態を直接表すのが特徴です。
一般動詞は単語数は無数ですが大きく分けて、
行動・思考感情・状態・会話
の4パターンに分けることができます。
主な例をあげてみましょう。
| 意味 | 主な一般動詞 |
| 行動 | run(走る), eat(食べる), read(読む) |
| 思考・感情 | know(知っている), like(好き), want(欲しい) |
| 状態 | live(住む), belong(属する), need(必要とする) |
| 会話 | say(言う), tell(伝える), ask(尋ねる) |
また一般動詞も時制や主語によって様々な形に変化します。
| 時制 | 例文 | 一般動詞の形 |
|
現在形 |
I play tennis.(私はテニスをする) | play(原形) |
| 現在形(三単現) | He plays tennis.(彼はテニスをする) | plays(三単現のsをつける) |
| 過去形 | I played tennis yesterday.(私は昨日テニスをした) | played(過去形にする) |
| 未来形 | I will play tennis.(私はテニスをするつもりだ) | will + play(原形) |
| 進行形 | I am playing tennis.(私はテニスをしている) | be + playing(現在分詞) |
| 完了形 | I have played tennis.(私はテニスをし終わった) | have + played(過去分詞) |
規則動詞と不規則動詞
英語の一般動詞は、
「過去形」や「過去分詞形」に変化する際に、規則的に変化するかどうかということで
規則動詞と不規則動詞の2種類に分けられます。
規則動詞
上記の例でいえば、過去形や過去分詞で表現するときにplayがplayedに変わっていましたよね。
これは規則動詞になります。
規則動詞と不規則動詞の違いをまとめるとこんな感じです。
| 分類 | 特徴 | 例 |
|
規則動詞 |
規則的に動詞の末尾に"ed"をつけて変化する |
play → played, want → wanted |
| 不規則動詞 | 特別な変化(単語の形そのものが変わる) |
go → went eat → ate |
規則動詞は動詞の末尾にedをつけるだけなので簡単ですが動詞のスペルによってルールがあります。
これもルールですのでぜひ覚えておきましょう。
規則動詞のスペル違いによるルール
| パターン | 例 |
| 語尾がeで終わる → dのみ | love → loved |
| 子音字+y → yをiに変えてed | study → studied |
| 短母音+子音 | stop → stopped |
規則動詞の単語のスペルが上記3パターンに当てはまらない場合は”動詞の末尾にedをつけるだけでOKです。
不規則動詞
不規則動詞についてはルールに当てはまらない特殊な変化をする動詞です。つまり全く別の単語になるということ。
こればかりは頑張って暗記するしかありません。
といっても不規則動詞は規則動詞ほど数も多くなく実際に英会話などでよく使う単語も限られていますので暗記できると思います。
下記の不規則動詞は英会話でも頻繫に使用する不規則動詞ですのでとりあえずこれだけでも暗記しておきましょう。
| 原形 | 過去形 | 過去分詞 | 意味 |
| go | went | gone | 行く |
| eat | ate | eaten | 食べる |
| see | saw | seen | 見る |
| have | had | had | 持っている |
| come | came | come | 来る |
| do | did | done | する |
| get | got | gotten | 得る |
| give | gave | given | 与える |
不規則動詞の覚え方のコツはただやみくもに丸暗記するのではなく以下のようにグループ別で分けると覚えやすいです。
| パターン | 例 |
| 変化なし | cut – cut – cut / put – put – put |
| 過去形・過去分詞が同じ | say – said – said / make – made – made |
| 過去形のみ変化 | come – came – come |
| 全て変化 | go – went – gone / drink – drank – drunk |
不規則動詞の中には上記のcutやputのように全く変化しない動詞もありますが、この場合はedをつける必要はありません。
というか不規則動詞にedをつけると文法上間違いですので注意しましょう。
自動詞と他動詞
英語の一般動詞には自動詞と他動詞というものがあります。
これも文法を学ぶ上では重要ですのでしっかりと理解しておきましょう。
自動詞と他動詞の違いを一言でまとめると以下のとおりです。
自動詞・・文の中で目的語を取らず、主語だけで動詞の意味が完結する動詞
他動詞・・目的語を必要とする動詞。主語だけでは意味が不完全になる
自動詞
自動詞は目的語を必要とせず
「誰に?」「何を?」
という情報がなくても文が成立します。
自動詞を使った例文をみてみましょう。
He runs every morning.(彼は毎朝走る)
She cried.(彼女は泣いた)
The sun rises.(太陽が昇る)
それぞれ、
「何を走る?」「何を泣いた?」「何を昇る?」
とはなっていませんよね。
全て目的語なし(自分の行動だけ)で意味が完結しています。
自動詞は
”自分の行動だけで意味が完結する動詞”
という覚え方でいいでしょう。
他動詞
他動詞は目的語を必要とし
”主語だけでは意味が不完全になる動詞”
です。
目的語とは”動作の対象(誰を?)(何を?)”を表します。
だから
「誰に?何を?」
という対象がなければ意味が成立しません。
他動詞を使った例文をみてみましょう。
He reads a book.(彼は本を読む)
I love you.(私はあなたを愛している)
She bought a car.(彼女は車を買った)
それぞれ、
「何を読む?」「誰を愛する?」「何を買った?」
という目的語(動作の対象)が動詞のあとにきていますね。
このように他動詞を使う場合は動詞のあとに動作の対象となる目的語がきます。
他動詞は
”自分だけで完結せず「他」に影響を与える(=目的語が必要)な動詞”
という覚え方でいいでしょう。
自動詞にも他動詞にもなる動詞もある
英語の動詞には
”文脈によって自動詞にも他動詞にもなる動詞”
もあります。
例えば”open"という単語は自動詞としても他動詞としても使用可能です。
自動詞:The door opened.
(ドアが開いた)
他動詞:He opened the door.
(彼がドアを開けた)
また"ran"は自動詞としては”走る”という意味になりますが”~を経営する”という他動詞としての使い方もします。
自動詞:He ran fast.
(彼は速く走った)
他動詞:He ran a company.
(彼は会社を経営した)
自動詞と他動詞は実際の会話の中ではあまり気にすることはありませんが英文法を勉強していく上で重要な予備知識となりますのでしっかりおさえておきましょう。












